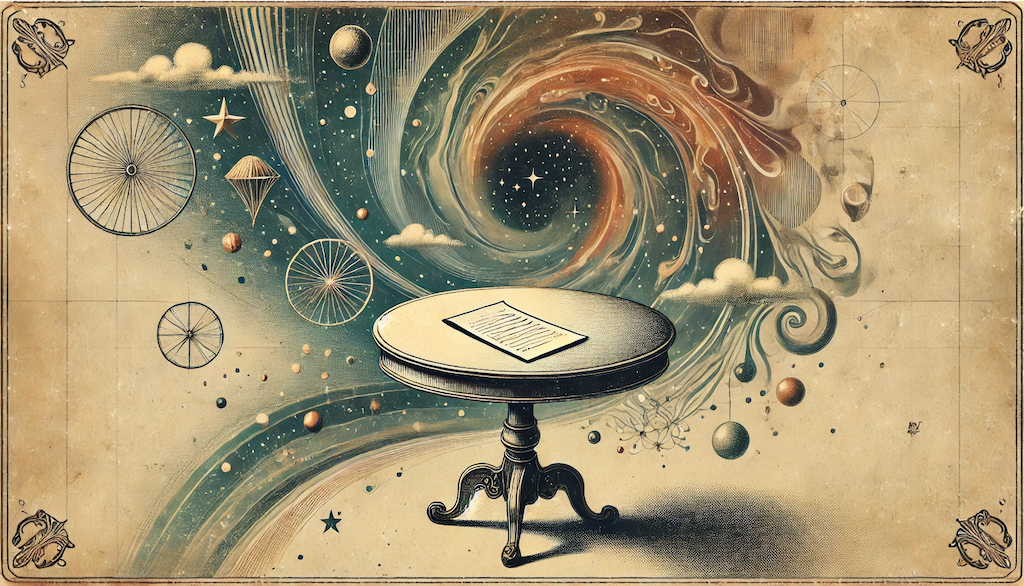
今さら、萩尾望都の名作漫画『トーマの心臓』を読んでみた。沼だった。
きっかけは、萩尾望都が大学で創作について語った講義が書籍化されるというネットニュースを見かけたこと。
創作本大好き人間だから、それだけ読んでもよかったんだけど、せっかくならと、Kindleストアで一番最初に目についた『トーマの心臓』を読んでみることにした。
電子書籍1冊で完結するとはいえ、なかなかのボリューム。布団に潜り込んでから、「あと、ちょっとだけ……」とKindle Paperwhiteを開いてしまったのが運の尽き。
すっかり寝不足である。
※以後、核心的なエピソードや結末などのネタバレはしないよう書いていますが、推しポイントやセリフを引用しているのでご注意ください。
オスカー強火推しになる運命だった
物語はギムナジウムの生徒、トーマ・ヴェルナー、13歳が自ら命を絶つところからはじまる。
家族や学校側は不幸な事故と思っているが、トーマが自殺したと知っているのが主人公のユーリ(ユリスモール)。
なぜなら彼は、トーマからの遺書(ラブレター)を受け取っていたからだ。
トーマの死の真相を知るのがもうひとり、ユーリのルームメイト、オスカーである。彼が自分の推しになることは、読み出してすぐに分かった。
第一印象は、冷めた微笑とタバコ(※未成年)がよく似合う美青年。
品行方正、成績トップ、マイナス点もスキャンダルもないユーリとは対照的で、授業はよくすっぽかすけれど、生徒たちへの統率力があって教師から一目置かれる存在。亡くなった母親と瓜二つの美形で、ギムナジウムに入って以来、父親からは5年以上音沙汰がない。
最上級生への物怖じしない態度(むしろかわいがられている)とか、自分がいちばん泣きたいだろうところで他の子に泣かれてしまうところとか、推しが推しすぎて語彙力失う。
各国で生まれた神話に類似性が見いだされるように、推しにもユング心理学でいうところの無意識の原型があるんだろうとつくづく思い知らされた。
どこに向かうのか予測不能の群像劇
夜更かしするくらい先を読まずにはいられなかった理由を考えてみると、まったく着地点が予想できなかったことが挙げられる。
読み出してすぐ、誰とそれがくっついてめでたしというBLではないと予想はついたけれど、それでどこに向かっていくのか予測不能だった。
ユーリやオスカー、トーマに瓜二つの転校生、エーリクをはじめ、主要人物みんなが解決すべき問題を抱えていて、群像劇として見る作品である。
それにしたって、ひとりひとりのドラマが濃厚すぎるのだ。たとえ鼻につくような生徒だって、思い詰めたような愛を垣間見せられたら切なすぎて、読者的にも切り捨てられない……。
まあでも、やっぱりブロマンス的にはね、ユーリとオスカーのコンビがマイベスト。ふたりきりのルームメイトでね、最初から抜きん出た信頼関係を感じさせてくれる。
たとえば、ユーリが家族に宛てた手紙を書くところ。自分は家庭というものが分からないから興味があるって、その中身をオスカーは読みたがるし、ユーリは嫌がるでもなくそのまま書き続ける。
クライマックス近くで、弱ったオスカーに対してユーリがかける言葉がもはやひとつの詩。
※一部引用します!
もしきみが……
ぼくが……ここにいていいのなら……
もしきみがだれか必要で
ぼくを好きなら……もしきみが……
男とか女とか、キスとかそれ以上とかの次元とは別。存在に対する愛そのもの。
ちょっと恐ろしくもあるけれど、思春期のときに読んでおきたかった類いの純度である。
恩田陸版『トーマの心臓』もいいぞ……!
恩田陸の長編小説に『ネバーランド』というのがある。冬休み、それぞれ訳あって寮に居残って過ごす4人の男子高校生の青春小説で、たしか作者本人が「自分なりの『トーマの心臓』をやりたかった」といっていた作品。
もともと人生のマイベスト10に入れているくらい好きな作品で、それがあったから萩尾望都を読もうと思って真っ先に『トーマの心臓』を選んだところもある。
何がすごいって、まず『トーマの心臓』を読み出してすぐ、『ネバーランド』って本当に『トーマの心臓』じゃん……! と思ったこと。
物語をトレースしているわけではないし、登場人物もエピソードも違うんだけど、それでも恩田陸版で『トーマの心臓』だったのだ。もう、どっちにひれ伏せばいいのか分からん(両方だよ)
推察するに、恩田陸が『トーマの心臓』で刺さったであろう要素を分解して、再構築したのが『ネバーランド』という気がする。
そのひとつが、少年たちだ。それぞれが重たいものを背負っていて、それに押し潰されないギリギリのところで、学校にいる。
彼らは不意に友だちの抱えているものを察するし、それで自分の荷がどうなるものでもないんだけど、相手を思いやる。そんないい子たちばかりなのだ。
それがまた「友だちだから」とかではなくて、嫌なやつ、反が合わないやつでも、同じく背負うものがある相手への分け隔てのない優しさがある。
息苦しくも温かい世界。手放しで肯定はできないけれど、この世界を生きるのもそこまで悪くない、と思わせてくれる作品たちだ。


